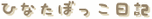家族の買ってきた野菜チップスが美味しすぎて止まりません。
野菜とはいえ揚げてあるのだから、食べ過ぎはいけないと思いつつも……。
続きにパラレル設定の短い文章をいれておきました。
比較的最近書いている文章は、結構書いたらすぐアップしてしまうことが多いのですけれど、以前に書いたきりのものが雑多に放置されています。
このへんもなんとかまとめなければ……と、storyeditorをダウンロードしてみました。
ブログツールで書いていると、うっかり窓を閉じたときに「あっ!」っとなってしまいますし、サーバだっていつエラー出すか分からないからローカルにも置いてあったほうが安心かなと。
しかしパソコンが壊れたり、外付けHDDやフラッシュメモリを失くしてデータが引っ張り出せなくなったことの多々ある身では、ローカルもたいがい不安だったりします。
どうやるのが一番安全なのか、今しばらく模索していそうです。
拍手を押してくださった方、どうもありがとうございます。
連打などされているのを見ると、きゅんっとなります。
もっと早く再燃していれば……と思うこともありますが、こうやって一緒に楽しんでくださる方がいる時に公開できたのは幸せなことだと感じます。
「結婚だと?」
親友の放った言葉がにわかには脳に浸透しなかったため、ロイエンタールはその単語を反射的に聞き返した。
「そうだ。そろそろ卿も考えてみたらどうだ」
一人勝手に頷きながら続けるミッターマイヤーに、ロイエンタールは無言を通した。
こういうときの彼はひとりでもしゃべり続けるので、いちいち言葉を挟んでいらぬ口論を呼び寄せたくはない。
「いいものだぞ。温かい手料理が毎日食べられるし」
シェフがいるから間に合っている。
「疲れて帰っても笑顔で出迎えてくれるし」
そういう存在なら既にいる。
「何と言っても、守るべき存在があるっていうのは生活に張りが出るしな」
二人も三人もいらん。一人で十分だ。
心のなかでだけ丁寧に反論しつつ、ロイエンタールはいつもの講釈を聞き流していた。
元帥府の廊下はやがて二人の分かれ道に差し掛かり、軽く挨拶を交わしてそれぞれの方向へ歩き出した。
・
・
・
「結婚?」
兄の親友が放った言葉をにわかには信じたくなかったため、ミュラーはその単語を反射的に聞き返した。
「そうだ。ロイエンタールもそろそろ女遊びをやめて結婚したらいいと、お前も思うだろう?」
いや、全く。どれだけの女性と付き合ってもいいから、このままずっと誰かたったひとりを決めないでいてほしいと思ってます。
とは口にはできないため、ミュラーは小さく唸るようにして首を傾げるだけに留めておいた。
「あいつが結婚すれば、お前の義理の姉になるのかな。お姉さん、欲しいと思わないか?」
思いません。
「うん。なかなかいいんじゃないか。ロイエンタールと奥さんとお前。3人仲良く暮らすのも」
兄さんとならともかく、兄さんの奥さんと仲良く暮らせるはずがない。
僕が永久に手に入れることのできない人を、横から簡単に掻っ攫っていった相手と仲良く出来るほどお人好しにはなれない。
兄と離れたくなくて一緒に暮らしたとして、二人が愛し合っている姿を見続けるだなんて耐えられないだろう。
そうなったら出ていくしかない。
行くあてなどないけれど。
黙ってうつむくミュラーに、ミッターマイヤーは続けた。
「ああ、でも、新婚と一緒には暮らしたくないか。ま、その時はうちにでも来ればいいさ」
どんなに仲のいい兄弟であっても、いつまでもずっと一緒にいられるわけではないのだから。
ミッターマイヤーが言葉にしてそういったわけではない。けれどこの話題の裏側にはそうした前提があってのことだろう。
二人の間に未来を約束するものなんて何もない。今更教えてもらわずとも分かっている。
分かっているけど、考えたくないことだった。
このままずっと一緒にいられるわけがないだなんて。
未来のことを考えると、弊害ばかりが重くのしかかってくる。
いつも自分に優しくしてくれる、2番目の兄といえるほど仲の良いミッターマイヤーにだって、この気持ちは理解してもらえない。
そもそも言えるはずもない。同性愛は法で禁じられているのだから。
誰にも言えない思い。応援されることのない恋。
それでも止められなかったのだから仕方が無いと開き直ってきたけれど、尊敬するミッターマイヤーにすら言えない思いを抱え続けるのはきつかった。
もし知られたら明朗快活なこの人にすら蔑まれる可能性は十分にある。
この気持はそういう類のものなのだ。
何かをこらえるように、ミュラーは手を強く握りしめた。
「……その話、兄さんにもしたの?」
「ああ。したさ。もう何度目かな」
なんてことを。
結婚の選択肢があるだなんて一生知らなければいいくらいなのに。
そうだな、結婚もいいな、だなんて思うようになったらどうしてくれる。
「兄さんは、なんて?」
「考えておこう、だと。あいつはいつもそうやってはぐらかすんだ」
・
・
・
「兄さん、結婚したい?」
夜になって帰宅した兄から、冬の軍用コートを受け取った僕は何気なさを装って口を開いた。
「なんだ? ミッターマイヤーもそんなことを言っていたが、どこかでそんな噂でもあるのか?」
襟元を緩めながら兄は訝しげな視線を送ってくる。
あまりさり気なくとはいかなかったようだ。
「そういうわけじゃないけど」
「それともおれに、誰かと結婚してほしいのか?」
してほしいわけないじゃないか。
などと言い返すわけにもいかず、僕は視線を逸した。
「別に、ぼくは……」
「もしおれが結婚するといったらどうするんだ?」
なんて残酷なことを聞くんだろう、この人は。
嫉妬にかられて泣いて喚くと思いますって言っていいのか。
でも現実には、そうするほどの勇気も出せないんだろうなと、なんとなく確信していた。
といって自分のことのように喜べるわけもない。
「……お祝いは、すると思うよ……」
嬉しくはないけど。
「しかしな、まだ手のかかるやつもいることだしな……」
「僕、手なんてかけてないよ」
頭に置かれた手に頬を膨らませながらも、僕にだけ手をかけていてくれたらいいのに、と、思わずにいられなかった。
僕が足かせになって結婚出来ないというのなら、嫌というほど手をかけさせて、一生の子ども扱いだって甘受したっていい。
「そうだったか?」
からかうような、優しい声。
いつか他の誰かに聞かせるだなんて、とんでもない。
この声は、手は、自分だけのものだ。少なくとも、今は。
「まあ、今のところは結婚などするつもりはない。したいとも思わんしな」
僕がむくれていたせいか、兄は髪をするりと梳いて、宥めるように額にキスをしてきた。
キスに胸が一瞬高鳴って、僕は足を止めてしまった。
少し遅れて兄の言葉を反芻する。
結婚するつもりはないと、兄の口からはっきりと聞きたかった言葉が聞けて、僕の機嫌はたちまち治ってしまう。
今のところは、と付いていたとしても、結婚願望がないだけでもありがたい。
足を止めた僕を気にすることなく、すたすたと歩いて行ってしまった薄情な兄を小走りで追いかけた。
結婚するつもりがないと知った今なら、軽口だって叩けてしまう僕は、我ながら現金なものだと思う。
「兄さんの連れてくる相手が嫌な人だったら、僕、グレちゃうかも」
それは困るな、といって、兄さんは笑った。
このままずっと、僕だけの兄さんでいて欲しいと、祈るように願い続けた。
願うだけならきっと、罪には問われないだろうから。